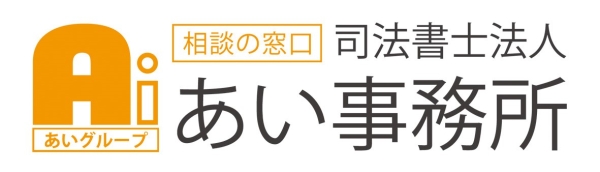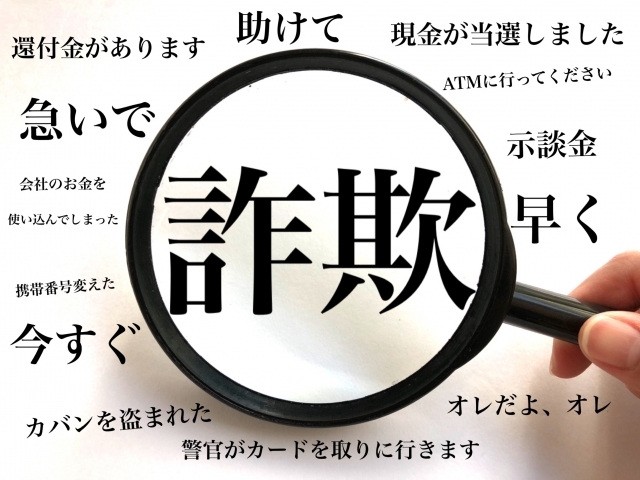法的な対策には、以下のような手続きがあります。
シニア支援協会では、司法書士と一緒にご相談に当たっております。
◎ 成年後見制度
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人を保護・支援するために、法的に権限を与えられた成年後見人等が本人の財産管理や身上監護を行う制度です。
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
〇 任意後見契約
任意後見契約とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ任意後見人に代理権を与える契約です。任意後見人は、委任された事務について、本人に代わって行うことができます。
任意後見契約は、公正証書によって結ばれます。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見契約の主な内容としては、次のようなものがあります。
u 財産管理:自宅などの不動産や預貯金、年金の管理、税金や公共料金の支払いなど
u 療養看護:生活状況に応じて、ヘルパーや訪問介護、介護施設などとの契約のサポートなど
〇 財産管理委任契約
財産管理委任契約は、自分の財産の管理や事務手続きを代理人に委任する契約です。
財産管理委任契約は、次のような場合に利用できます。
u 身体的な不自由などで、外出が困難になった場合
u 判断能力はあるものの、自分では財産管理をすることが不便な場合
u 事故や病気によって、心身の状態が思わしくない場合 等
◎ 法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に利用できる制度で、家族や第三者が申立できますが、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかに分類されます。法定後見人となり、財産管理や生活支援を行います。
これらは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで適切に行うことができます。
1. 家を売って施設に入居するための費用を確保したいが、売却行為ができない
2. 定期預金の解約ができない(引き落としができない)
3. 介護施設への入居、介護サービスの契約が(自分判断では)できない
4. 悪徳商法などの消費者被害にあいやすくなる
5. 通帳や実印など、大切なものの保管場所を忘れてしまう
◎ 遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)
遺言書とは、亡くなる前に自分の意思を表明して、財産をどのように分配するかを記載した法的な書類です。民法に定められた方式に則って作成する必要がありますので、作成する際は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
遺言書を作成しておくと、財産分与や相続の内容を自分の意志に沿って定められ、認知症発症後もその内容が尊重されます。
遺言書を作成することで、法定相続分とは異なる相続の配分や、法定相続人以外への遺贈が可能になります。
◎ 家族信託
家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、その家族に財産管理や運用、処分を任せる民事信託の形です。財産保有者(委託者)が、財産に関する利益を帰属させる者(受益者)のために、特定の者(受託者)に財産を託す仕組みです。
家族信託は認知症対策として注目されており、意思・判断能力のあるうちに家族へ管理や運用を託すことで、認知症を発症しても財産の有効活用が可能になります。